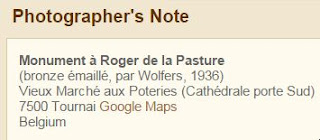「ミナサン、ミナサンハ、イツタイ、ナニガオカシイノデショウカ」
かえってきたのは教室全体を揺るがす大笑いだった。
著者はこれが文章語だったと書いている。この日以来、まわりの子たちの話す言葉を注意深く聴くようになって、話しことばとしての日本語が文章語としての日本語と全く異質なことに気づく。
現代の日本語は「口語体」で、話しことばと書きことばが一致した「言文一致体」である、という教科書に記されたウソに身をもって気付かされた。
同書の同じ場面を論文で引用した日本語学者の小池清治氏は、説明している。
どの言語においても、口頭言語(話しことば)と書記言語(書きことば)とは厳密には一致しない。なぜならば、口頭言語は音声を媒介とし、書記言語は文字を媒介とする。口と耳を便りとする表現と文字と目を便りにする表現とは自ずから異質な表現体系をなすからである。そのようなわけで、「言文不一致」となるのが言語の自然なのである。(「『言文一致運動』の展開に見る日本・中国の相違」宇都宮大学国際学部研究論集 2001、第12号)専門家によってこのように解説されると「やはり」言文一致はないのだとこっちも確信が持てる。一般には「言文一致」とは話すときに使うことば遣いで文を書くということと思われているようだ。そのようにして書かれた文体が言文一致体であるとも。まして教科書にそのように書かれていれば、誰しもそうかと思う。そんなことはないのに、ずっとそのように言われてきた。だから小森氏は幻想だと言っていつも括弧つきで書く。
この本は著者が自分の言語形成過程について書いてみないかという提案を受けたのが動機で書いたと明かしている。出来上がった本書は日本語がうまく出来なかったことに端を発して皮肉にも国文学者になり、さらに教職について広く異文化研究に進んだ体験が語られている。その体験が多様であるだけに個々のトピックに関して読者も自分なりに関心事の材料が与えられる楽しみもあった。
著者が知識も学力もない国文科で困ったのは卒業論文だ。少しはましな特技はロシア語しかないところから二葉亭四迷の翻訳小説の文体と翻訳の質を分析することをテーマにして辛くも卒業できた。
論文の出来はさておいても、このテーマの選択は成功だった。二葉亭の『あひゞき』でツルゲーネフの翻訳の問題から取り組みはじめた。
参考文献を集めだしてみると、近代の日本語、とりわけ小説における『言文一致』体の成立をめぐって、この『あひゞき』の翻訳が決定的な意味をもっていたことがわかってきましたし、日本で最初の『言文一致』体小説としての『浮雲』が成立するうえでも、この『あひゞき』の翻訳が重要な転機になっていることも見えてきました。(中略)あらためて、翻訳という過程をとおして、ある言語システムにおける新しい表現の変容が発生することに気づかされることになります。ここで著者が驚かされたのは、ツルゲーネフにとっても、『あひゞき』の収められている『猟人日記』を書くことが、詩人から散文作家に変わる転機になり、そこに翻訳という問題がかかわっていたことだった。ツルゲーネフがフランスに滞在していたとき、すでにフローベールなどによっていわゆる視点描写、つまり作品の内部に身を置いている特定の作中人物の感覚に即して、外界を叙述するという表現方法が創出されていた。となれば、『猟人日記』中の作品は文学先進国のフランスに学び、まずフランス語でロシアの自然を書き、それをロシア語に翻訳するというプロセスを経て成立した可能性が見える。同じ事が二葉亭の中でも起こっていたのではないかと思ったそうだが、これは正解で二葉亭自身が、まずロシア語で書いてから日本語に直した、という苦心をどこかで語っている。小森氏はこの卒論の作業を通じて「近代『言文一致』体とは、実は翻訳言語であり、翻訳文体ではないか」という感触を得た。
旧ソ連のロシア語学校では小学校低学年では「祖国の語り」という学科と「ロシア語」の二つが日本の「國語」教科にあたる。高学年では「祖国の文学」と「ロシア語」になる。「ロシア語」では書き取りなどを通して言葉のスペルを覚え、文法が叩きこまれ、それに基づいた作文がある。「祖国の語り」の教科書には近代ロシア語の基礎を築いたプーシキン以後の著名な表現者の散文や詩が、自然や人事をめぐるあらゆる領域にわたって収録されている。「國語」も「社会」も「理科」もみな含まれる総合科目になっていた。
帰国した日本で出会った國語教科書にはそのような豊かな内容はなく、文章も半端で短く、二日もあれば読み終えてしまう退屈なものだった。授業の退屈さはそれどころではなかった。まず「段落分け」という作業があって、これが何のためやら、さっぱりわからなかったという。何でも「形式段落」と「意味段落」があって、最後にまとめの作業がある。教科書には「学習の手引」という部分があって「作者の気持ちを考えてみよう」とか「登場人物の心の動きを整理してみよう」とかの問いがある。教師はそれらに短い文で当たり障りのない正解を提示する。これが授業だった。
一つの物語のある場面における作中人物の気持ちを語り始めたら無限にあるはずなのに、どうしてこんな単純化される結果になるのか不思議だった。
ロシア語の「祖国の語り」教科の授業は生徒が教科書の文章をまるごと暗記して、それを表現力豊かに発表するのだった。これが唯一の指導方法ではないだろうけれども、そのクラスでは定評ある文章や詩を元の形をこわすことなく生徒が自分で操ることのできる表現として身体に刻み込んでしまう方法をとっていたわけだ。「水準の高い言語表現を暗記して再表現するということは、そのことばを自らの言語にしてしまうことにほかならない。『祖国の語り』の授業は、生徒が声を出す場であり、教師は生徒の発表に対し短いコメントをするぐらいだった」という。作品について生徒同士の議論はあっても、教師から均質的な解釈を求められることはなかった。
はて、全体主義で思想統制されていたはずのソ連なのに、教師からの制約はなかったのかと疑問に思ったが、時代は既にフルシチョフの頃だ。ベルリンの壁が出来たりしたけれど、初等教育は別なのか。よく分からないが著者が書くとおりであったのだろう。
「祖国の語り」の授業に比べて、「國語」の授業では生徒は沈黙を強いられ続け、教師が誘導尋問した時だけ答えを言うことが出来る。しかもそれはあらかじめ予定されているのだ。「國語」の授業は何とも息苦しい時間に思えたと回想する。
「教科書ガイド」を買って読めば全部出ていることをあとで知る。そこには黒板に板書される事柄すべてが載っているのだ。これを丸暗記すればテストで100点も可能になる。
小森氏は書いている。「後に、高校で『國語』の教科を教えることになって、『教科書ガイド』なるものが、それぞれの教科書に、教科書会社が附録としてつけている『教師用指導書』なるものに従って作られていることを知り、『國語』という教科の解釈中心主義が、『國語』という市場全体を支配する構造的なものだったことを理解することにな」った。
この辺まで読んで考えこんでしまった。教室で「段落分け」をさせられるというのを読んで、そういう経験がないのでネットで調べてみた。すると、用語の解説以外に、何のためか、どうすれば分かるか、とか授業に出ていればわかるだろうにと思える質問がたくさんあったのに驚いた。50年たっても同じことが行われている。
「段落分け」が教科に入っているのは、なにごとも外国を手本にしようとして明治20年代の文部省が国定教科書の文章に段落をつけたからだそうだ。段落は一字下げることだけが一般に伝わったが、それにまとまった意味があるなど知らなかった。先生もわからないから教えない。教えられない。段落は英語のパラグラフであって、元来日本語にはなかったものだから國語では気にする必要はなかった。(外山滋比古『國語は好きですか』大修館書店 2014)
人間性を育てる教育とか謳っていながら、千差万別の考えが出て来そうなクラスで答えが一つとは問題だろうと思う。数学や実験結果じゃあるまいし。ここに政治の作為はないのだろうかと疑う。教科書会社はサービス過剰とも思うが、ひょっとして学校側が望んでいるのかもしれない。教科書をこなせる教師がいないのではなかろうか。
ロシアにロシア語の教科があるのなら日本には教科として「日本語」があってもよいはずが、義務教育にあるのは「國語」だ。教育の歴史に「國語」が登場しても不思議ではないが、現代の義務教育にも昔のままに「國語」があるのにはなにか目に見えない意志の力を感じる。
小森先生が工夫した授業の実践例を三つ、ライヴ記録として載せている。私が一番びっくりしたのは高校生と読んだ『どんぐりと山猫』だ。言わずと知れた宮沢賢治の作品、一般には童話として知られているし、もちろんその通りに読んで構わないが、ここでは紙背に隠された事柄を拾い出す作業をしている。出てくる答えは一通りであるはずはないが、ここに誌された報告をおもしろく読んだ。おそらくこのライブ授業から20年たった今では同じような読み解きが普通になっているかもしれないが、私には初めての体験であった。かつて私が読んだのは小学校から中学2年までの間、70年も昔だ。初期の『注文の多い料理店』という一冊だったが、面白いお話として強く記憶に残っている。おとなになっても、それを新たに読みなおして分析しようとは思いつかなかった。今回は青空文庫の新字新かなで読んだ。原文は賢治の作法として、同じ語に平がなと漢字の使い分けをしているので、青空文庫の校正は信用できるにしても、読むほうにとってはやや心許ない。
ライヴ記録『どんぐりと山猫』は自由の森学園高等学校二年生、1996年2月。教室には落ち葉がたくさん敷かれていて風も吹いている(扇風機で!)、と舞台の説明があった。はじめに小森先生が授業の趣旨を説明する。読者の一人一人には違った読み方があり、話し合うことでいくらでも多様な豊かな意味が見いだせる。最初に全体を先生が朗読し、次いで生徒が自由に意見や疑問を出して議論するという形をとる。ジャズのジャム・セッション風。各人が各自の楽器を好きな音色でアドリブをする感覚で進行する。楽器で音を出す場合と違うのは、各人が思ったことを声で外に出す前に言葉にしなくてはならない。そのとき思ったことがそのまま言葉で伝えられるとは限らない。大抵少しずれたようになる、相手がどう受け取るか、それをまた修正する、こうして言葉で発信して議論することが鍛錬される。朗読の後、初版の『注文の多い料理店』発売に際して、賢治自身が書いた宣伝文の中の「どんぐりと山猫」についての文章が紹介される。
山猫拝と書いたおかしな葉書が来たので、こどもが山の風の中へ出かけて行くはなし。必ず比較をされなければならない今の学童たちの内奥からの反響です。この文章にセッションの狙いもあることを知らせて討論に入る。この宣伝文は初めて知った。朗読が終わってからセッションが始まるせいか、物語の終わりに近い部分から討議が始まっている。金色に輝くドングリたちが、誰が一番エライかを問題にしてわいわいがやがや、「めんどなさいばん」である。高校生たちは、偉いってなんだろうとの疑問にぶつかる。物差しが要ると立会の教師が口を出して助ける。小森先生は比べるって事が大事だ、と補足する。「必ず比較をされなければならない学童」、人間を比較するとはどういうことか、物差しで何をはかるのか、考える。偉いという「抽象的な価値の基準は、その世界のなかでは決められなくて、外の権威に頼らなければならないわけだね」と小森先生。最後にはいちばんエライのは天皇か、との発言もあって、賢治の時代ならクラス全員死刑だと笑いもでる。ここで終業のチャイムが鳴ってしまったので、小森先生がまとめるが、授業の発言と進行に沿った説明からは自ずから近代日本の過去の姿勢も例に出された。「どんぐりと山猫」という物語には食う、食われるという食物連鎖、自然と人間への視点も内包されている。
普通なら素通りしてしまう言葉の意味内容に対する感性がとぎすまされる。「どんぐり」から何を引き出すか、「とびどぐもたないでくなさい」の意味は何だ、深く考えればいろいろな事柄や問題が見えてくる。
「このなかでいちばんばかで、めちゃくちゃで、まるでなってないのがいちばん偉い」(一郎の発言)と、「このなかでいちばん偉くなくて、ばかで、めちゃくちゃで、てんでなっていなくて、あたまのつぶれたやうなやつが、いちばん偉いのだ」(山猫の発言)と、どうちがうのか、違いを見つけるのはまるで哲学のようだ。
自由の森学園は私立学校だからこんなこともできたのだろう。公立校なら教師用指導書のとおりに上滑りして一つの答えだけで終わりになるのだろうか。そもそも『どんぐりと山猫』は危険思想だから(!)公立では採用されないかも。
第8章に「心と体で表現する日本語」という章がある。言葉には意味とコンテクスト(文脈、あるいは背景情報)があり、会話では意味はわかっても、相手の生活環境や文化によるコンテクストがわからなければ円滑な会話にならない。教師がコンテクストのずれに気が付かないことが教育場面にも多いことが述べられる。
要約すれば、こういうことになると思うが、実は理解しにくかった。ここには平田オリザ氏との対談の一部が載せられていて、平田氏の指導するワークショップの例題を使って対談が進む。その対談で本文を補足する意図だろうが、プロの二人の対談がそのまま読者に理解されるとは限らないだろう。著者の手抜きか編集の失敗だと思う。読者のためにはそれこそ対談のコンテクストを補うべきだったのでないか。
平田氏はワークショップでコミュニケーションのためのコンテクストのすり合わせなどを指導している。本書発刊当時と違って現在ではウェブサイトがあるので、それを参照することで理解できた。
「あとがき」の結びには「『ふつうの日本人』や『ふつうの日本語』という幻想から、私たちが自由になり、各自の個別的な言語実践を肯定できるようになることを心から願っています」とある。
「ふつうの日本人」や「ふつうの日本語」というのは帰国児童の小森クンが劣等感を抱いた対象を指している。後に分かってみれば、すべてまやかしだった。極論すれば日本人はみんな個別の心の奥底にあるものをどこかに置き忘れて、うわべだけの人間になっている。ほかの人と同じ、みんなと同じでありたいとの願望に生きているみたいだ。
とにかくこの書物は面白く読ませるかのようにみえて、実はそうではない。随分考えることがありすぎるくらいだ。あえてまとめて言うとすれば「國語」がおかしい。総ては明治に始まっている。
(2015/12)