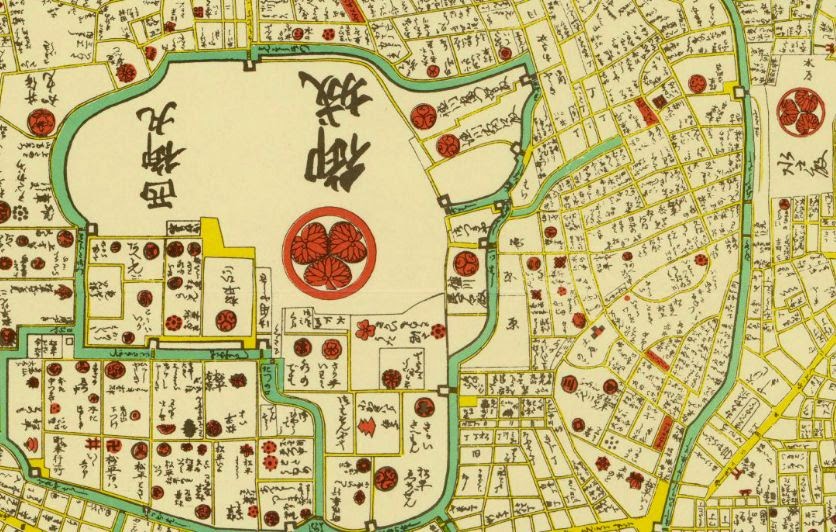|
| 1936 初版と著者署名 |
記憶をたどれば最初はNHKテレビの地方ニュースで川越の「さつまいも友の会」の発足を知ったことだった。アメリカ人の大学の先生が川越の名産を知って自分の国にもあることを伝えたことから芋文化研究サークルができたと報じられていた。
一番強烈な印象はアメリカではサツマイモの産地が出荷する際のレーベルのコレクターがいることだった。紹介されたいくつかのレーベルにはまさに日本人が知っているサツマイモそのものが描かれていたのである。出荷用の木箱に貼るレーベルであるから一般消費者の目に触れることはないらしい。
1998年にインターネットという道具ができて、筆者はさっそく利用して数々のラベルを楽しんだものであった。
ラベル収集家用のサイト例;
http://www.thelabelman.com/index.php?cPath=36_60
あれから30有余年「川越いも友の会」は大きく発展して今ではサントリー文化財団の支援も受けているらしい。発端を作った大学の教授はベーリ・ドゥエル(Barry Duell)氏で、川越在住を契機にサツマイモ研究に打ち込み論文「アメリカさつまいも事情」を出版、ネット版も大いに参考になる。日本語版がある。
www.suntory.co.jp/sfnd/prize_cca/detail/1991kt1.html
http://www.tiu.ac.jp/~bduell/sp/usasp/
こうして遅まきながらアメリカにもサツマイモがあるということを知ったあと、あるとき『風と共に去りぬ』(原著1936年))を読んだ。図書館の蔵書で読んだのだが、分厚い一冊本の大久保康雄・竹内道之介共訳であった。古い話なので今その図書館の検索にかけても、それらしい書物が見当たらない。世界文学全集の一冊と思うが、三笠書房という記憶がかすかにあるだけで確かではない。いずれにしても初期の翻訳であったろう。大久保康雄氏による単独完訳が成ったのは1938年とされていて、それは絶版になったらしい。その後、竹内氏との共訳ができて、両者の没後も現在まで出版社を変えて発売されている。

写真は映画『風と共に去りぬ』(1939年)の一コマ、アシュレのガーデン・パーティに出かけるため衣装合わせに忙しいスカーレット。マミーに手伝わせて自慢の17インチのウエストに合わせてコルセットを締め上げる場面、世間ではかなり評判になったショットだ。
マミーはオハラ家の令嬢が守るべき鉄則、つまり出先でなにも食べなくてすむように食事をとるように勧める。映画ではこのとき別の家政婦が料理を大きなお盆に乗せて運んでくるが、原作ではマミーが呼ばれた時にすでに自分で持って二階に上がってきている。
さてその料理の盆の上には、
バターを塗った大きなじゃがいもが二つと、シロップがたれるそば粉のホットケーキと、肉汁の中を泳 ぐハムの大きなかたまりがのっていた。
(新潮文庫昭和52年初版、大久保康夫・竹内道之助訳)ここで筆者が問題にするのはスカーレットやその細いウエストのことではなく、「じゃがいも」と訳されている食物のことだ。
上に記した場面で「じゃがいも」となっている食物が、のちに見た同じ訳者による版では「さつまいも」になっていて、おや、と思ったことがある。さらにその後、気になって見た同じ訳者の別の本には「じゃがいも」に戻っていた。おや、おや、である。その後、現在手元に買い揃えた新潮文庫(平成十一年)は上に述べたとおり「じゃがいも」だ。 (末尾 追記参照)
あるとき、新潮社にこの変遷の経緯を問いただしたことがあるが、なしのつぶてであった。訳者はすでに故人であり、出版社も三笠書房、河出書房、新潮社と変わる間にはそれぞれの浮沈があり、この作品は何よりも絶版になっていたものを戦後復刊してベストセラーになったいわくつきだ(注1)。その上、大久保康雄氏は多くの下訳者を駆使した翻訳工房の主である。筆者の質問などとるに足らぬ些事であったことに加えて、調査する手立てもなかったのかもしれない。最近になってネットで知ったが同作品の翻訳の正誤に関しては、レットが訣別を告げるセリフ(注2)やタラの丘でまたレットを取りもどそうと誓うスカーレットのセリフ(注3)がファンの間で取り沙汰されていたことを知った。芋のことはますます些事になっていたのだ。
(注1)三笠書房HP企業情報の沿革によれば、1937年本邦初訳で出版、1948年ベストセラー、とある。Wikipedia 竹内道之助の項には、1940年大久保訳を刊行するが発禁、戦後大久保と共訳の形で再刊しベストセラー、翻訳歴に同書が共訳1954となっている。確実な情報がほしい。
(注2)
“My dear, I don’t give a damn.”「だが、けっしてきみをうらんではいないよ」(大久保訳)
「知ったことか」(映画字幕 松浦美奈)
(注3)
After all, tomorrow is another day.「明日はまた明日の陽が照るのだ。」(大久保訳)
「明日に希望を託すのよ」(映画字幕 松浦美奈)
で、問題の些事にもどる。筆者は些事を些事とは思わないから、サジを投げるわけにはいかんのだ。
この作品は歴史小説でもあり、社会史でもあると思う。その中で筆者は単純に芋の種類に目が行っただけなのだが、そもそも、われわれ日本人がある時期まではアメリカにサツマイモがあるなどとは考えてもいなかったし、事情を全く知らなかった。戦争中におとなだった人たちの中には、サツマイモと聞いて代用食や空襲下の自家菜園などを思い出してアメリへの恨みの残り火をかき立てたかもしれない。いまでこそ、インターネット情報もたくさんあるし、アメリカのラジオも聴けることから状況がわかってきたのである。
『風と共に去りぬ』が映画(1939)になってからも冒頭の場面で料理は映らない。もし、翻訳者がひょっとしてサツマイモ?とでも疑念を持てば、そこは専門家としてアメリカ側に問い合わせるなどの手もあったかもしれない。事情はわからない。
ちなみに映画の日本公開はようやく戦後の1952年9月だ。余談になるが一部の日本人は上海などで戦前にこの映画を見て、こんな大作の映画を作る国が相手との戦争にはとても勝てない、と慨嘆した話がある。
マーガレット・ミッチェルは同作品の中に登場する「いも」を四種類の語で表示している。
yam、yelow yam、potato、sweet potato である。
大久保氏の翻訳ではyamとyellow yam、potatoは「じゃがいも」、sweet potatoは「さつまいも」としている。sweet potato pieの場合には、スイートポテト・パイとなっている。
前出の東京国際大学のドゥエル教授によれば米国では,yamは肉がオレンジ色のサツマイモの意味であるという(「アメリカ サツマイモ事情」米国のサツマイモ祭りヤンボリー)(注)yellow yamについての説明はない。
こういう次第なのでオハラ家の農園および食卓の場面に描かれるyamはサツマイモなのである。
『風と共に…』の中でタラの丘が北軍に荒らされた際、食料が洗いざらい持ち去られた後、芋だけは助かった。理由は北軍のやつらは土の下に食物があるなどとは知らなかったからだ。奴隷のポークは喜んだ。
「丘の上の芋畑は?」(原文は"Even the sweet potato hills?)
「スカーレット嬢さま、芋を忘れてましただ*。きっと畑に残ってるにちげえねだ。ヤンキーどもは、さつまいもを見たことがねえだで、きっと何かの根っこだと思って――**)
* Ah done fergit de yams.
**Dem Yankee folks ain'never seed no yams an'dey thinks dey's jes' roots an'――.
ここでは先にsweet potato hills が出ているからあとのyamsがサツマイモと判断できたのだと思われる。
それではyellow yamはどうなのだろう、筆者の考えでは大久保氏の「じゃがいも」でも作品の鑑賞上は支障がないと思う。
それではどんな料理なのだろうか。第1部の4章にある、新潮文庫(一)117ページ。
While Gerald launched forth on his news, Mammy set the plates before her mistress, golden-topped biscuits, breast of fried chicken and a yellow yam open and steaming, with melted butter dripping from it.蒸した山芋?を割ったところにバターをのせた一品がフライド・チキンと共に供されるのだとは思うがどうだろう。ジャガイモのほうが感覚的にはぴったりだが。
ジェラルドが新しいニュースについて弁じはじめると、マミーは、上のほうが黄金色にこげたパン菓子や、鶏の胸肉のフライや、とけたバターがぽたぽたしたたり落ちて、あたたかそうに湯気を立てるジャガイモなどの皿をならべた。(筆者注:ジャガイモは訳文ではひらがなに傍点がつけてある)(大久保訳)
ステーキに付けるじゃがいもは四つ割りにしてホース・ラディッシュをのせるがあんな感じかと思う。あるいはお祭りの屋台で売っているジャガバタだ。結局大久保氏の苦心の訳も空揚げにジャガバタというイメージでいいのではないか。となれば、yellow yamは日本にはなくて日本名もないのだから、ここは食卓の雰囲気を出すためにジャガイモを正解とすればよかろうと思う。ただし、湯気が立っているのは猫舌の西洋人のテーブルには似合わない。
英文のネット情報ではJamaican yellow yamがyellow yamと呼ばれているように書かれていて、皮をむくときには痒くなると注意がある。図像もあってヤマノイモに非常に似ている。その仲間としてwhite yamもあり、この図像はサトイモそっくりである。日本でも、どちらも皮をむくとき皮膚が痒くなることはよく知られているから同じような種類だろう。
とはいってもアメリカ人はものの名前に厳密さはあまりこだわらないから、中身が黄色がかっていれば赤みがかったサツマイモと区別しただけかもしれないし、なんともいえない。ただ、ここのイメージから形は丸っぽいほうがありがたい。
筆者はシンガポールの華人との食卓で食後のスイートに汁粉状の小鉢を出されたことがあり、訊くと「ヤムです」という答えが返ってきた。少しねっとりとしてミルクコーヒーのような色をしていた。このヤムは東南アジアに産する植物で、サツマイモではない。このようにyamはどこをどのように伝わったかは知らないが同名異物がたくさんある。
『風と共に…』はアメリカでも大人気であったことに関連して『「風と共に去りぬ」のクッキング・ブック』もあれば、サツマイモ料理のレシピもたくさんあって、日本の女性にもファンがいるように見受けられる。筆者が苦心して何年もかかって正体を突き止めたヤムも近頃の奥様方は簡単にブログで情報を交換している。アメリカの11月第4木曜日、Thanksgiving Dayにはターキーなどとともにサツマイモ料理が習慣になっているのも、今では皆様方の常識みたいだ。南部の経験者は少ないように見受けられるが、時代は変わった…遥けくも来たものかな…だ。
Duell教授は彼の論文に芋の栽培分布図を載せているのは参考になる。
一説に、ジャガイモはアイルランド移民がアメリカに持ち込み、独立戦争では兵隊の食糧に大いに役立ったという。
http://www.tiu.ac.jp/~bduell/sp/usasp/p02.sp.vs.pot.html
たかが「いも」の問題でずいぶん長い間、頭の隅が掃除できなかったけれども一応これで問題が片付いたことにする。yellow yamの料理はいずれ時が解決してくれるだろう。
最後に蛇足。『風と共に去りぬ』の翻訳で大久保康雄氏といつも名前が並んでいる共訳者、竹内道之助氏は三笠書房の創業者であるが、最近のNHK連続テレビ小説「花子とアン」では小鳩書房社長、門倉幸之助として登場していると聞いた。演じるのは脳科学者の茂木健一郎さんとか。
(2014/12)
【追記】
その後発見した筆者の古いファイルには、『河出文学全集22 風と共に去りぬ Ⅰ』(河出書房新社 1989年)ではサツマイモとなっていると記録されている。訳者は上述と同じ共訳である。
(2015/1/28記)