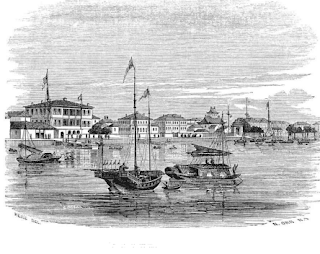この間、澁澤栄一のことを少し調べたときに読んだ露伴全集第17巻には渋沢栄一伝を含めて史伝6篇がおさめられてあり、なかに「日本武尊」が入っていた。読むでもなく眺めると、書きぶりが面白い上に、言葉についての探求がこの人らしく、惹かれるものがあったので一通り読んでみた。日本武尊という人物は実在しないというのが今日の定評であるけれども、ここに収録された文章のもとは昭和3年の新聞連載である。探究心旺盛だった露伴のことであるから、日本の古代についてはある程度、それも並の人以上に知識を持っていたろうと思う。素知らぬ顔をして淡々と語る叙述には、執筆者の用語、記紀に表現された和漢の言葉、また、それぞれの音声と文字、今と違う漢字の使い方など、筆者の関心が強いところが次々に繰り出されてなかなか興の深いことであった。すべてを書き出すことは出来ないが、かいつまんで記しておこう。
本文に先立って「緒言」が2頁半ほどある。講談師の枕のような語りで理屈が述べてあるが、真面目風でいて面白く述べるのがこの人らしい。時代や境遇の違いが大きく懸け隔たっている物事を理解することは難しいことだから、それを人に伝えるには、余程注意して控えめにしなくてはならないと心得を説く。今を以て古をはかり、己を以て他を律することは慎めと諭す。こういうときに露伴はなんとレンズの講釈を持ち出すので不意をうたれる。歪みや色収差の多い硝子鏡(レンズ)から覗いたままを真実とするとき、往々にしてレンズの持ち主の身勝手であることが多いものだと訓戒を垂れる。「クラウン玻瓈(ガラス)から覗いた世界は如実であるやうでも色収差に累(わずらわ)せられている、単レンズから覗いた世界は如実であるやうでも歪んでいる。自分がクラウンガラスの単レンズであろうことを憂ふる心づかひを存せぬ譯にはゆかぬ上からは、餘程謙遜した、控へ目の料簡を以て、古の勝れた人々に對したい。……」このあとにフリントグラスやら半球蛍石やらエナガラスやら、聞き慣れない語彙が並ぶ。どれも今でも生きている光学系の用語である。「…レンズが優良で無い時は、精々遠慮して絞りを強くするのが忠実に写真を撮る道である。是非はありません。控え目に、小心に、十分に絞りを入れて、今レンズの蓋を明けまする」と述べて緒言を終わる。
本文は一から四十に分けられ、150頁余り、日本武尊の出生から西征と東征までの事柄について、日本書紀にもとづいて、ときには古事記の記事とも比べながら語る。昭和3年の新聞に連載した文章だが、ことは皇室に関わる題材だけに敬語がしっかり使われている。そのぶん時代のなせることではあるにしても、露伴の生真面目な精神が窺われて好もしい。それだからといって堅苦しくはなく、古い言い伝えの荒唐無稽さをも楽しむ雰囲気をもたらしている。たしかに露伴はこの作品をたのしんで書いたろうと思える。
さて、本文は次の文で始まる。
日本武尊(やまとたけのみこと)(ママ――筆者注)の御上を意(こころ)の随(まま)に記したり談(かた)つたりすることは、まことに畏れ多いことである。それは尊(みこと)がただに皇子の貴(たっと)き御身であらせられたといふばかりで無く、また皇朝第十四代の足仲彦(たらしなかつひこ)天皇、御諡號(おんおくりな)仲哀天皇の御父君にわたらせられた御方であるといふばかりで無く、我が国家人民のために、いろいろと御労苦あそばされて、そして大いに皇化を賛(たす)け、世益を圖らせられた御方であり、そして又大勲偉業を立てさせられたにもかかはらず、光栄幸福の日をおくらせられるにも及ばずして、御壽も猶ほ花ならば咲きの盛りに至らず、月ならば光の圓(まどか)なるを示されざるほどの御齢(おんよはひ)に、口惜しくも嵐に散り、雲に隠れさせたまうたゆゑに、千七百餘年後の今に於いても、尊の御上を思ひ奉れば、誰しも胸の中に何とも申し難いやうな肅然たる感を抱かずには居られないからである。ただし今尊の御上を、かにかく申すのも尊を思いしのびまつる餘りのことである。まことに畏れ多く、罪得がましいことではあるが、しばらく宥恕(いうじょ)を得たい。こういう調子の日本語は久しぶりである。読んで快感さえ覚えるのはわが歳のせいか。「罪得がましい」など何とも奥ゆかしく響く。千七百餘年後の今、とあるが、これは新聞に連載した昭和3年のことだ。昭和15年に紀元2600年祭というのが催された。当時7歳の筆者は、祖母に連れられて寒い中を橿原神宮に詣ったのはよく覚えている。「キゲ~ンワニセ~ンロッピャクネン」と歌う歌もあった。
神武即位を西暦紀元前660年と決めてかかっての2600年目が西暦1940年すなわち昭和15年に当たる。露伴先生はこの皇紀創出作戦とは無関係のはずだから、何らか別の根拠で1700年余りの時間経過を考えていたわけだろう。いずれにしろ、人か神かもよくわからない実在が疑われる存在の履歴であるから、とは言わないまでも、露伴は系譜やら紀年については、あまり真っ正直に考えないほうがよいと、それとなく教えてくれている。
文には日本武尊は第十二代景行天皇の第二皇子とある。原文を見てみよう。日本書紀は漢字だけの文で、読みや注釈を示すときには少し小ぶりの漢字を用いた。ここでは[ ]内に示す。日本武尊についての記事は、『日本書紀』では「景行天皇紀」に記述されている。これは尊が若くして亡くなって天皇にならなかったからの扱いである。
二年春三月丙寅朔戊辰、立播磨稻日大郎姬[一云、稻日稚郎姬。郎姬、此云異羅菟咩]爲皇后。后生二男、第一曰大碓皇子、第二曰小碓尊。[一書云、皇后生三男。其第三曰稚倭根子皇子。]其大碓皇子・小碓尊、一日同胞而雙生、天皇異之則誥於碓、故因號其二王曰大碓・小碓也。是小碓尊、亦名日本童男[童男、此云烏具奈、]亦曰日本武尊、幼有雄略之氣、及壯容貌魁偉、身長一丈、力能扛鼎焉。概略を訳す。(景行天皇は)3月3日播磨のイナヒノオオイラツメを立てて皇后とした。皇后は男子を二人生み、第一の子を大碓皇子(オオウスノミコ)、第二の子を小碓尊(ヲウスノミコト)と申された。この二人は同じ日に生まれた双生児であった。天皇はこれをあやしんで臼にちなんだ名をつけた。この小碓尊はまたの名を日本童男(ヤマトオグナ)、また日本武尊(ヤマトタケノミコト)と申される。幼くして雄略の気があり、壮年には容貌魁偉、身長(みのたけ)は一丈あって、その力は鼎(あしがなへ)を持ち上げられた。
私たちが普通にヤマトタケルノミコトとよぶに対してヤマトタケノミコトとしてあるのはどこから出たものなのか。一説にタケルは悪い評価のある人への称え、尊い人にはタケとするというが、定説はないようだ。ここに云う「またの名」は自称ではなく、人よんでこの名もあるという意味だと思う。
双生児が生まれることを異とする理由はわからないが、露伴はお産がなぜ臼と関連するのか考えようとしている。ウスにはいろいろあるが、碓は「からうす」を意味する文字である。だからといって字面にこだわるのは了見が狭すぎる、広く伝承を探れば何かあるのかもしれないと、徒然草まで引っ張り出して各地のウスに関する民俗伝承をいろいろあげて読者を楽しませてくれるものの結論はない。
原文をうかつに読めば、后を娶ってその年に男子二人が生まれたかのように見えるが、そうではないと読み方に注意している。それは(天皇在位の)27年冬10月の条に日本武尊を遣って熊襲を討たせる話があって、そこに年16とあるからである。したがって、日本武尊の生年は天皇の御代第12年の生まれとなる。この天皇は治世60年の冬に御崩(かく)れになリ、御年106歳とあるから、逆算して、この時天皇は58歳になっていた勘定だ。日本武尊の生年はそれでいいとしても、天皇の年齢については考えないほうが良かろうと諭す。景行天皇については父垂仁の37年に皇太子となって、21歳だったと紀にあるから、在位99年の垂仁が崩じて、景行が即位したのは83歳となり、治世60年なら143歳で崩御のはず、先に述べた106歳と食い違う。これは一例であって、一人の天皇だけでも幾通りもの人生が出てきかねない。
露伴いわく、「一體に古史の紀年は甲乙の齟齬が多くて、深く憑(よ)るに足らない。それは上代に暦術が精(くわ)しかったり、記録係が備へられたりした譯では無くて、文書の事が起ってから後に推算逆行して歳月を記したものであるからで、記紀の出来た前に既に種々家々の記も存して居たらうことは疑も無いが、それらの記にしても然程(さほど)遠い古から出来たものでは無からうから、数百年を隔てた歳月の注記などが精確であり得る道理は無い。[……]むしろ疑はしきを疑はしとして錯誤脱漏あらんと思って置くが宜い。重箱の隅を楊枝でせせっても得るところは無からう」と述べている。
話は前後するが、露伴という人は言葉に敏感に反応する。古代のいわゆる大和言葉による語彙を一つ一つ慈しむかのように検討する。「碓」のことや、「おぐな」についてなど、個々の例をいちいちここにはあげないが、それぞれ頁を費やすに暇なしである。かと思えば漢語の方にも博学ぶりを覗かせる。例えば、雄略について。いまの私達は雄略と字を見ただけであらかた見当はつくからそれでよしとするが、露伴はいちいち立ち止まらなくては収まらない。雄略は「一つの語とも取れるが、漢文の辞法で雄才大略をいふ」のだそうである。「谷川士清は実に詳しく紀を読んでいること敬服すべきだけれども此字面を看過してゐるが、秦鼎(はたかなえ)は流石に漢学者で、これを漢武紀に本づいてゐると指摘してゐるのは、人各々其道によって賢いものだ。雄材大略は漢書の語で、漢の中で最大膨張を敢えてした「武帝を贊した班固の語を採り用ゐて…熊襲、蝦夷までを掃討して天日の光を廣布された尊の御上を、幼にして雄略の気有らせたまひ、と紀の撰者が筆を下したのは、まことに感服なもので、所謂良工に苦心多きものであるのに、庸人多くは做す等閑の看で、うっかり讀過しては濟まぬくらいのものである」とあって、あとは日本書紀の文章が一代の最高才識の結晶であると賛美する。
古人は良い本を熟(よ)く讀んで、じっとりと味はってゐるから、其の發するところの文も、片言隻語亦おのづから來歴ありで、中々手堅い美(うま)いことを爲(し)てゐる。紀の文章なども、日本文学草創時代では有り、漢文を以て國史をものするといふ難局にも當面してゐるのであるから、其の困惑の情状は推察に餘りあるのであるが、それでも全體を通じて論ずれば、どうして中々立派に出来てゐるのであって、用語措辭に至っては感服すべき用意が盡くされてあることを否むわけには行くまい。紀の文章語辭の出典のあらましも見透せぬ分際で兎角を云ふのは、自ら省みて差控へたいことである。壯に及びて容貌魁偉、身長一丈、とあるのなどは、たゞ然様(さう)いふことを然様(さう)記したまでであろうから誰も注記もしないが、後漢書郭太傅に、身長八尺、容貌魁偉、とあるのと字面も辭氣も甚だ近いものがある。力能く鼎を扛げたまふとあるのは前人も指摘して居るが、史記の項羽本記に、籍長(せきたけ)八尺餘、力能く鼎を扛ぐ、とある其の四字一句を其儘移したので、尊の御勇力のほどを譬喩的にあらはしたのだが、此等は我知らず胸中の文字に累されたものであろう。鼎(あしがなへ)などいふものが此時代に餘り無かったものらしいから、まだしも宜いが、若し鼎が数々當時の談話中にあらはれて、そして重いものとされてゞも居たならば、甚だ好ましからぬ文飾であった。このように述べておいて、そのあとに身長一丈や八尺の寸法論議が5頁ほども続くが、面白いけれども煩わしいから省く。それよりも身の丈高く容貌魁偉で力が強い人となりならさぞ乱暴者でもあったろうと想像させる記事が古事記のほうに見出される。御兄君を拉(とりひし)がれた逸話である。
御父天皇が小碓命に詔(の)りたまふやう、何とかも汝(みまし)の兄(いろせ)の朝夕(あしたゆうべ)の大御食(おほみけ)に参出来(まいでこ)ざる、専(もは)ら汝泥疑(ねぎ)教へ覺(さと)せ、と詔りたまうた。然るに如是(かく)詔りたまひて以後(のち)、五日といふまで猶も参出たまはなかった。そこで天皇が小碓命に問ひたまふには、何ぞ汝の兄の久しく参出ざる、若し未だ誨(をし)へず有りや、と問ひたまうた。尊は、既にねぎつ、と申したまうた。如何さまにか泥疑つる、と詔りたまうた。そこで尊は答へ白(まを)したまふに、朝曙(あさけ)に厠に入りたりし時、待捕へて搤㧗(つかみひし)ぎて、其枝を引闕(ひきか)きて、薦に裹(つつ)みて投げうちつ、と答へたまうたといふことである。記には又直(すぐ)に其段につづけて、そこで天皇は其御子の猛く荒き御情(みこころ)を惶(かしこ)みまして、それから、西の方に熊曾建(くまそたける)二人あり、これ伏(まつろ)はず禮(あや)無き人どもである、其人等(ひとども)を取れ、と詔りたまうて、そして尊を西方にお遣はしになった、と記してゐるのである。天皇が尊の勇猛をかしこみたまふと云ふが如きは、天皇の御心中に立入ったことで、甚だ以て慎言の用意に遠いことである。もとより記さなくても有るべきことである。…尊が兄王を扱われたこと、及び天皇が尊の勇猛をかしこみたまひたること等は其事も不分明であるし、其情も未だ必ずしも然らざるべきものであるから、疑はしきを闕(か)き、晦(くら)きを袪(しりぞ)けて、諱(い)みて書さなかったのであらう。我等がかゝる事をかにかくと談(かた)るのは、古を考へて詳(つまびらか)ならんことを欲するの意からとは云へ、齊東野語の陋に陥ってゐるもので、本来は深く論ぜぬ方が賢いことであらう。また後ろの方で、尊の仕業も言葉だけのことかもしれず、本当にあったこととも思われないような書きぶりをしている。「諱みて書さなかったのであらう」とは、筆者の都合で露伴の話の一部分を抜かしてしまったが、尊の荒業は『日本書紀』には書かれていないことを指している。
食事時に出てこないことについて、人間にとっての共食は大昔から禽獣とは異なる人の道、礼として大事なことと訓戒をたれ、ことに大御食は宮中儀式としても大切であったであろうと例によって諄々と説いて、皇子が勤める必要もあった場合もあったとしている。泥疑を音で読ませて字義を持った文字を当てていないのは、ネギの語が含蓄が多すぎるくらいの語であるからだと、7世紀の渡来人の官僚の心遣いまで思いやって述べているのである。
ねぎといふ語は禱(いの)るのもそれである、犒(ねぎ)らふのも無論それである、願ふのもそれであるが、和(な)ぎ、和ぐ、和(なご)し、和む、和(にぎ)ぶ、にぎはふ、なだむ、なぐさむ、撫(な)づ等の語と聯(つら)なってゐる語で、そして祈禱願求犒労等の意にもなり、神に仕ふる者をねぎ、なぎなどともいふのである。参出べき筈の皇子が参出られぬのは、何かいぶせく心晴れぬものが有るからなのであらう、それを然様(さう)で無いやうに、泥疑教へ覚せと宣うた」わけであるから、ここは「和(なご)しく優しくといふやうに解したい。」「泥疑の一語が含蓄甚だ多くて、禱、願、犒等の字を用ゐただけでは其の意義景象を盡し難い趣が有り、且邦語其儘を用ゐた方が、写し得て霊活なので、そこで文面上には見づらく無くも無いが、泥疑と借音文字を敢てしたのであらう。大碓皇子の大御食不参にまつわる逸話の結末は曖昧朦朧として霞の彼方である。不参の理由も父天皇の命に背いた行為をしてしまった大碓皇子自身の心のとがめにあったことが後に語られてはいるが、ただ読み過ごすだけで面白ければいいようなことだ。
何がどうしたところで、すべてがおそらく伝承である。岡田英弘著作集「日本とは何か」によれば、ヤマトタケルは天武天皇の影であると断じる。壬申の乱の出来事がすべて二重写しに記されていると明らかにする。古事記は日本書紀より後に書かれた。古事記にあって日本書紀にない事柄は日本書紀が求めた風土記が日本書紀完成時に間に合わなかったためであり、そのため日本書紀にない事柄が古事記に載せられることになった。大御食にまつわる変事もいまは失われた風土記の何処かにあったのかもしれない。岡田氏は『古事記』は偽書であると断言されている。ここに詳しく引用することは出来ないが、平安朝の作品だそうである。平安朝文学の傑作と評しているが古代の真実に迫る手掛かりとしては役に立たない。兄、天智天皇の息子である大友皇子を、実力で倒して皇位を奪った天武天皇が着手した国史の編纂は、681年から39年かかって720年に完成した。これが『日本書紀』である。日本最古の古典であるが、最古は必ずしも真実ではない。ちなみに『古事記』の序文の日付は和銅5年、すなわち712年、太安万侶の名はここにだけ出ている。風土記の編纂が命じられたのは713年だ。あとから書いた『古事記』にはより多くの風土記の内容が盛り込まれている。「因幡の白うさぎ」の言い伝えもその例である。
露伴がいくら詳しく考証しようとも伝承が史実に変わることはないが、考証してくれている事柄はおそらくどこかにあったはずのことであろう。その考証の過程から地名の変遷、言葉の意味の変化、伝承芸能の誕生、まつりの発生、暮らしの習俗の変化などが生じてきたことなどが考えられる。日本文化の探求として興味がそそられる。筆者はもっと直接的に露伴の遺した文章表記に興味がある。ことば、音声、文字、漢字、漢語、など。明治の頃に西洋知識を吸収しようと西洋文字の文章に取り組んだ人々は漢英辞典を利用したと聞く。ならば以後日本文に使われている漢字の熟語には本来和語であるべきものに漢語が当てられていることもあるだろう。西洋語が意味した内容を日本語用の頭脳で考えて日本語にした場合とのずれもあるはずだ。露伴の文字の使い方にはそのあたりがうまく出ているように思えるので深く読んでみたい。たまたまヤマトタケルに出逢ったが、筆者にとっては話の中身は史実でなくても構わないのである。この度はこのような関心から書き出したのであったが、あれこれと目移りがしてまとまりのないことになってしまって残念であるがこのままにしておく。
そうそう、『日本書紀』景行天皇紀の「二年春三月丙寅朔戊辰」がどうして今でいうところの「二年春三月三日」であるとわかるのか。これまでは詮索するのが面倒だからフンフンと読みすごしていたのだったが、今回リクツを勉強した。十干十二支をあわせた六十干支表を教わった。インターネットは誠に重宝な道具であるにしても、それを使って細かく説明してくれる方もいること、原文の提示も同じく、本当にありがたいことに思う。
読んだ本:『露伴全集 第17巻』(岩波書店 昭和54年第2刷、第1刷昭和24年)(2018/12)